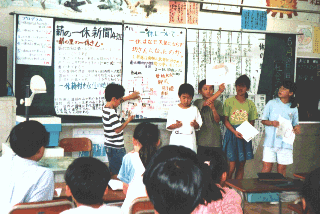 薪小学校の校区内に、一休寺(酬恩庵)があります。私達の学級では、
社会の学習に合わせて、一休禅師について学習をし、班毎に発表をしました。
薪小学校の校区内に、一休寺(酬恩庵)があります。私達の学級では、
社会の学習に合わせて、一休禅師について学習をし、班毎に発表をしました。その内容の一部を紹介します。
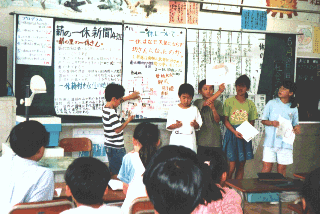 薪小学校の校区内に、一休寺(酬恩庵)があります。私達の学級では、
社会の学習に合わせて、一休禅師について学習をし、班毎に発表をしました。
薪小学校の校区内に、一休寺(酬恩庵)があります。私達の学級では、
社会の学習に合わせて、一休禅師について学習をし、班毎に発表をしました。
その内容の一部を紹介します。
| 1394年(応永元年) | 0才 | 一月一日、京都で生まれる。 命名「千菊丸」。 |
| 1399年(応永六年) | 5才 | 京都にある禅寺「安国寺」に入り 像外艦和尚の弟子になり、「周建」という名を与えられる。 |
| 1405年(応永十二年) | 11才 | 一休は大変賢くて、安国寺での 勉強では足りなくなったため、「壬生寺」の清叟仁和尚について学ぶ。 |
| 1406年(応永十三年) | 12才 | 建任寺の慕詰はん和尚に 詩を学ぶ。 |
| 1409年(応永十六年) | 15才 | このころから貧しい人や学問のない 人たちのために、よいお坊さんになろうと考えるようになる。 |
| 1410年(応永十七年) | 16才 | 西金寺の謙おう和尚のところへ移り 「宗純」と名を変える。 |
| 1414年(応永二十一年) | 20才 | 謙おう和尚が亡くなり寺を出る。 |
| 1415年(応永二十二年) | 21才 | 滋賀県の琵琶湖の近く堅田という ところにいる華叟和尚の弟子になる。 |
| 1418年(応永二十五年) | 24才 | 華叟和尚から「一休」という名を もらう。 |
| 1420年(応永二十七年) | 26才 | 5月20日の夜明け、 琵琶湖の船の中で悟りを開き、それ以降旅に出る。 |
| 1428年(正長元年) | 34才 | 華叟和尚の病気を知り、 お寺へ帰って看病するが亡くなる。そこで、一休はまた旅に出る。 |
| 1432年(永享四年) | 38才 | 奈良や大阪を歩く。 |
| 1467年(応仁元年) | 73才 | 京都の町の近くにいるときに応仁の乱が 起こったため、前にいたことのある薪村に逃げ、酬恩庵に住む。 |
| 1469年(文明元年) | 75才 | 7月。薪村にも戦いが広がってきたため、 大阪の南の方へ逃げる。 |
| 1474年(文明六年) | 80才 | 薪村へ帰り、天皇の命令で大徳寺の和尚になる。 また、天皇から紫の衣をもらう。 |
| 1481年(文明十三年) | 87才 | 10月21日。薪村の酬恩庵で亡くなり、 丘の下にほうむられる。 |