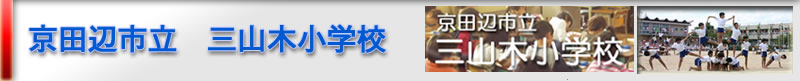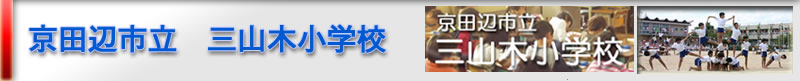平成14年度
研究実践内容及び成果と今後の課題
授業改善部
1 実践内容
(1)年間指導計画への教材等の書き込み作業
(2)研修会(8月22日)
「算数科における基礎学力の充実と授業改善」
皇學館大学 文学部 勝美芳雄先生
(3)授業研究会
・4年 国語 「ごんぎつね」 (10月29日)
・5年 算数 「面積」 (11月 1日)
(4)授業改善の取組まとめ(各学期ごと)
2 成果と今後の課題
成果
(1)少人数授業について
ア 人数が少ない分、一人一人に関わることができ、理解が不十分なところが明 らかになり指導しやすかった。
イ 習熟度別のグループでは、その子にあった授業ができるため自分のペースで学習を進め、主体的に取り組もうとする児童が増えてきた。
ウ 課題別のグループでは、興味・関心が同じ児童が協力し合い、インターネット等を活用しながら意欲的に取り組むことができた。また、それぞれの成果を交流しあう場を持つことにより、お互いのよさを知ることができた。
(2)授業改善について
ア 授業研を実施し、少人数授業について全校で話し合う場を持つことにより、成果や課題が明らかになった。
イ 低学年では学年で教材・教具の工夫をし、授業改善に取り組むことができた。
ウ 少人数授業での学習の成果(表現力をつけるための取組・視聴覚機器の利用)を他教科に生かし、また、反対に他教科で学んだことを少人数授業の中で活用するという相互関連の取り組みができた。
課題
(1)少人数授業について
ア 習熟度でクラス分けをするときに、児童の希望と学力に差があり、希望を優 先すると学力差が開きすぎるため、人数の多いクラスで一人一人の児童への指導が十分できない。そのため、担任+少人数加配+1名という体制が必要となってくる。
イ 休み時間が短い場合移動がスムーズに行われないため、来年度は週程表の中で休み時間について考えていく必要がある。
ウ 宿題・忘れ物等のチェックができない場合(児童の係り活動)教師がチェックし連絡する等の方法を考えておく必要がある。
エ 算数・理科等の教具・備品の数が不足しているので、今年度中に確認し、来年度に向けて購入計画を立てることが必要である。
オ 理科の実験は、教室では実施できないので、実験のある単元について少人数授業の内容を考えていく必要がある。
カ 習熟度別の学習で進度がそろっていないため、途中での入れ替わりができない場合があった。入れ替わりを可能にするためには、途中で進度をそろえる等学習計画をしっかりと立てておかなければならない。
キ 算数科では診断テスト等でコース分けの基準がはっきりしているが国語科の習熟度別の基準について考えていかなければならない。
ク 意欲・関心・態度については発表回数の記録や振り返り以外に評価の基準を明きらかにしていく必要がある。
(2) 授業改善について
ア 授業研の実施時期については、事前研の持ち方も含め、年度当初に計画を立てておく必要がある。
イ 少人数授業を実施していない学年については授業改善のテーマがしぼりきれていなかったので、授業改善部として、両方にかかわったテーマが必要である。
ウ 総合的な学習の時間や生活科の授業の中にも、少人数授業のよさを生かしていくことが必要である。(特に単学級の場合)
(3) その他
ア 年間指導計画への人材記入(講師)だけでなく、講師依頼状を保管し、来年度の学習へ引継ぎをすることが大切である |