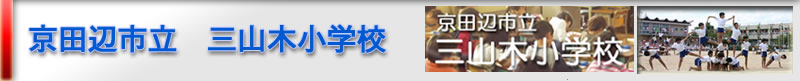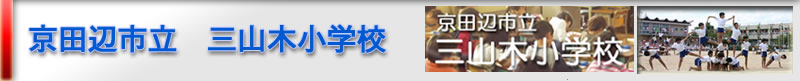平成17年度
研究テーマ
「子ども、教職員、保護者、地域がともに学びあい、育ちあう学校をつくろう」
研究の方向性(テーマ)を決定するにあたって
(1)学校とは
学校とはどんなところか考えるにあたって、 3 つの視点より考えることとした。
①子どもにとって学校とは、基礎的、基本的な学力を身につけ、学び育ちあう場である。
②教職員にとって学校とは、専門家として学び育ち合う場である。
③保護者・地域にとって学校とは、学校の教育に参加し、連帯して学び合う場である。 |
と定義することができる。そして、この 3者がそれぞれ有形、無形に協力、支え合ってこそ学校の改革ができると確信している。
(2)児童の様子とこれまでの経過より
これまでのさまざまな取組の中で、本校の子どもたちは確実に変化してきている。朝のチャイムと共に始まる全校読書、朝学習、各クラスでのさまざまな取組が学習への意欲や規律を生み出すもととなっている。また、児童会を中心とした活動も児童間の連帯を生み出すのに大きな役割を果たしている。もちろん根底には、教職員間の実践の交流と意思統一があることは言うまでもない。
しかし、なお多くの課題を残していることも事実である。基礎学力の充実、聴き合い、学び合う仕方の獲得、基本的生活習慣の確立、しっとりとした人間関係の樹立等多岐にわたっている。こうした課題に挑戦するために本校では、『学びの共同体』としての学校の創造を研究の方向として設定したのである。
(3)つけたい力とは
①子どもたちにとって
・基礎的基本的学力を身につける
・聴きあい、学びあう学びの仕方を身につける
・静かで、しっとりとした人間関係を身につける
・基礎的、基本的生活習慣を身につける |
②教職員にとって
・授業を公開し、同僚性を身につけ、専門家として成長する
・全体のテーマに基づいた各自の研究、実践テーマを持つ |
③保護者・地域にとって
| 学校の教育実践に参加することにより、学びと連帯を身につける |
研究内容
(1)授業研究部
①テーマ『学び合う授業』の創造
②学びを中心とする授業とは
ア 「活動的で共同的で反省的な学び」
物や教材と対話し、仲間や教師と対話し、自分自身と対話する学びを授業の中心にすえる。具体的には、作業のある学び、グループ活動のある学び、自分の分かり方を作品として表現し、仲間と共同して吟味しあう活動のある学びを組織すること。個から出発して仲間との共同を経由して再び個に戻ってくる学び。
イ 「よく聴き合う教室、授業」
一人一人の言葉を「聴くこと」「味わうこと」への変革。教師の言葉や教室の友達の言葉に対する「対応」によって何かを喚起されること、その喚起されたものを自分自身の言葉として結晶させ、その言葉を教材の内容や友達の言葉と刷り合わせていくこと。
ウ しっとりとした教室
一人一人の息遣いとそのうねりがやわらかく感じ取れる教室。
③授業研究への姿勢
ア 教師一人一人が自分のテーマを持ち、授業研究会を自分のテーマ追及の場として位置づける。
イ 授業のうまい下手は問わない。それぞれの特徴を生かした学び合う学びの存在する授業を目指す。
ウ 中心授業は指導案を作成するが、公開授業は必ずしも細かい指導案はなくても良い。授業の流れ等が分かる簡単なものでよい。
エ 公開授業は全員がする。
研究のまとめ
「学びの共同体としての学校をつくろう」という方向性のもと、2年目の研究となった。今年度も国語の研究を中心としながら、幅広く公開授業も実施してきた。また、基礎学力の充実を目指して朝学習や補習にも力を入れた。さらに、学習環境を整え、地域・保護者との連携を模索してきた。こうして、私たちが目指す学校像が見えてきつつある。
1 成果
* 3つの研究授業と多くの公開授業を実施する中で、お互いに教室を開き合い、学び合うことができた。
* 学び合う授業のあり方について形態や指導過程などに創意工夫が見られるなど一定の前進があった。
* 朝学習の取組が定着し、一日のスタートがスムーズに切れるようになった。
* 高学年を中心に学習困難な児童への支援ができた。
* 学力分析の交流をすることにより、児童理解が進んだ。
* 図書ボランティア、学年・学級への保護者の学習参加などが進んだ。
* 言語、学習環境の整備が進んだ。
* 児童の学習への意欲や態度が向上してきた。また、生活面でも比較的落ち着いてきた。
2 課題
* 学び合う授業のイメージとそこに至る授業の段階を明確にする。
* 文学や説明文そのものについて指導のあり方を深める。
* ノート指導についての研究を深める。
* 学力保障のあり方や方法についてより明確にする。
* 学習を支える基礎部分の取組や保護者の学習参加のあり方について深める。
* 言語・学習環境のよりいっそうの活用を図る。
* 目指す学校像をよりいっそう明確にし、全ての教職員が一致して取り組めるようにする。
|