![]()
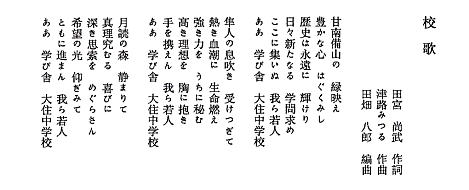 |
| 概要 |
| 沿革史 |
| 大住中学校区は、東部は木津川を隔てて城陽市と、北西部は八幡市と、西部は大阪府枚方市と接する京田辺市北部地域にあり、「関西文化学術研究都市」に隣接している。大規模開発で住宅地が広がる生駒山系北辺の甘南備山から続く丘陵地域と、伝統的な集落と水田の中に工場群が目立ってきた木津川沿岸の近郊農業地域からなり、自然が残された落ち着いた住環境となっている。 |
|
この地域は、古くから木津川の交通の利を生かして開発の進んだ地域であり、学校付近には古墳時代中期の大住車塚古墳、同後期の松井横穴古墳群などがある。奈良時代には九州南部の隼人の一族が大隅半島からこの地に移住して朝廷に仕え、宮中儀式の警護や歌舞を務めたといわれ、「大住」の地名の由来となった。また、中・近世においては、経済・社会・文化の先進地域として発展し、伝統的な村落共同体が形成されていった。 |
|
近代には、地元有志を中心に学制に先駆けて小学校開設に取り組み、明治6年(1873年)には綴喜郡内の9校の一つとして「進徳校」(現大住小学校)が開設された。また、自由民権運動もさかんで、府会において地元選出議員が活躍するなど、進取の気性に富んだ地域でもあった。 |
| 戦後、昭和26年(1951年)には田辺町に大住・草内・三山木・普賢寺の各村が編入され、現在の行政区域となった。地理的な位置と交通の利便性によって、高度経済成長以降、昭和40年代から宅地開発が進み、昭和40年代後半には松井ヶ丘地区が生まれ、昭和50年代に入って京都府住宅共通公社による大住ヶ丘地区の大規模開発が行われ、昭和53年(1978年)から入居が始まった。この開発に伴う生徒数の急増によって、昭和54年(1979年)4月6日、田辺中学校から分離して大住中学校は開校した。 |
| その後も田辺町は宅地開発、学研都市構想に基づく施設の開発が進められた結果、平成7年(1995年)の国勢調査で人口が5万人を突破し、市制に向けた諸条件も整備され、、平成9年(1997年)4月1日をもって市制が施行されて京田辺市となった。 |
|
校区は、大住小学校区、桃園小学校区、松井ヶ丘小学校区および薪小学校区の一部からなっている。現在、さらにJR松井山手駅周辺の大規模な住宅開発、第2京阪国道国道・第2名神高速道路の工事等が進められる予定であり、学校を取り巻く教育環境や地域社会の大きな変化が予測される。 |