| 学力状況の把握 |
 昨年度までの取組を踏まえ、学力診断テスト等を中心に、授業や定期テストなどで日常的に生徒の学力実態を把握するよう努めました。 昨年度までの取組を踏まえ、学力診断テスト等を中心に、授業や定期テストなどで日常的に生徒の学力実態を把握するよう努めました。
 学力診断テスト等の結果 学力診断テスト等の結果
第1学年 数学科基礎学力診断テスト(府中研数学部会)
第2学年 府中学校学力診断テスト
第3学年 校内実力テスト(年6回実施)
 小学校基礎学力診断テスト結果等、小中連携を通じて把握した学力の状況 小学校基礎学力診断テスト結果等、小中連携を通じて把握した学力の状況
 定期テストの結果 定期テストの結果
 教科の授業、生徒指導や教育相談等の状況から 教科の授業、生徒指導や教育相談等の状況から
 (今後に向けて)1年生入学後、2年生進級後の適当な時期にCDTテストを実施するなど、個々の生徒の学力実態をより客観的に把握し、学習課題やその克服のための具体的な手立てを明確にする必要があります。 (今後に向けて)1年生入学後、2年生進級後の適当な時期にCDTテストを実施するなど、個々の生徒の学力実態をより客観的に把握し、学習課題やその克服のための具体的な手立てを明確にする必要があります。 |
| 課題に応じた学習教材の開発 |
 個々の生徒のつまずきを段階的に克服させるための学習教材の充実、開発を進めました。 個々の生徒のつまずきを段階的に克服させるための学習教材の充実、開発を進めました。
| 教材名 |
対象 |
教材の特徴 |
分量 |
数学
「基礎の計算」 |
全学年 |
・生徒が自分で計算に取り組める。
・つまずきやすい少数・分数から平方根までの基礎的な計算に習熟する。
・1シート10〜20問で生徒の学習意欲を継続させる。
・【*point】で計算上の留意点を示して自主学習に配慮。
・取組表(チエックシート)、解答集を作成。 |
97シート |
英語
「基本文型・単語の練習」 |
全学年 |
・生徒が英語の基本文型・文法等の理解、習熟に取り組める。
・各学年ごとに基本文型練習と単語練習で構成。
・1シート内に、基本文型の日本語訳、英文法、英作文等を準備し、関連付けながら自主学習ができるように配慮。 |
77シート
+
48シート |
 (今後に向けて)開発した学習教材の効果的な活用と生徒の多様な学習課題に対応できるより多くの内容で段階的に構成された学習教材の開発が必要です。 (今後に向けて)開発した学習教材の効果的な活用と生徒の多様な学習課題に対応できるより多くの内容で段階的に構成された学習教材の開発が必要です。 |
| 個人別学習プログラム |
 個人別学習プログラムを、「個々の生徒の学力実態の把握、学習課題の設定、課題克服のための学習計画、その取組過程と評価を一つのサイクルとした指導の継続」ととらえ、個々の生徒についてそれらを総合的に把握するために3種類のシートからなる「生徒個人票」(個別学習カルテ)を作成し、充実を図りながら活用を進めました。 個人別学習プログラムを、「個々の生徒の学力実態の把握、学習課題の設定、課題克服のための学習計画、その取組過程と評価を一つのサイクルとした指導の継続」ととらえ、個々の生徒についてそれらを総合的に把握するために3種類のシートからなる「生徒個人票」(個別学習カルテ)を作成し、充実を図りながら活用を進めました。
 詳しい内容は、京都府山城教育局発行(平成17年3月)の 詳しい内容は、京都府山城教育局発行(平成17年3月)の
『個人別学習プログラムを活用した指導事例集−基礎学力充実実践研究校の実践から−』
を参照してください。
 (今後に向けて)個別的な指導と併せて生徒全体に共通する学力の課題を明らかにし、学校全体の学力向上を図る取組を進める必要があります。 (今後に向けて)個別的な指導と併せて生徒全体に共通する学力の課題を明らかにし、学校全体の学力向上を図る取組を進める必要があります。 |
| 基礎学力充実指導員と校内補習 |
 基礎学力充実指導員を活用した校内補習「ステップアップ学習会」を実施しました。 基礎学力充実指導員を活用した校内補習「ステップアップ学習会」を実施しました。
 毎週火・木・金曜日の放課後、数学科・英語科を中心に、学年別に実施しました。 毎週火・木・金曜日の放課後、数学科・英語科を中心に、学年別に実施しました。
 数学科と英語科を中心に、基礎学力指導員(英語科)と学年担当教諭が指導に当たりました。 数学科と英語科を中心に、基礎学力指導員(英語科)と学年担当教諭が指導に当たりました。
 全校生徒・保護者に案内し希望者を募集、また個別に勧め、70名余りの生徒が参加しました。 全校生徒・保護者に案内し希望者を募集、また個別に勧め、70名余りの生徒が参加しました。
 週1回の補習のため、部活動と両立でき、1年生を中心に進んで参加する姿が見られました。 週1回の補習のため、部活動と両立でき、1年生を中心に進んで参加する姿が見られました。
 基礎学力充実指導員の専門性(英語科)を生かし、教材の開発ときめ細かな指導ができました。 基礎学力充実指導員の専門性(英語科)を生かし、教材の開発ときめ細かな指導ができました。
 (今後に向けて)個別的な指導や校内補習など基礎学力充実の取組を学校全体でさらに組織的、計画的に推進していく必要があります。 (今後に向けて)個別的な指導や校内補習など基礎学力充実の取組を学校全体でさらに組織的、計画的に推進していく必要があります。 |
| 情報の発信 |
 ホームページを通じて取組概要の情報を発信し、学習教材を提供しました。 ホームページを通じて取組概要の情報を発信し、学習教材を提供しました。 |
| その他 |
 市内各中学校ブロックごとに設立された「学力向上推進委員会」と連携し、学力実態の把握と交流、国語科、算数・数学科の公開授業等の取組を小学校と連携して取り組みました。 市内各中学校ブロックごとに設立された「学力向上推進委員会」と連携し、学力実態の把握と交流、国語科、算数・数学科の公開授業等の取組を小学校と連携して取り組みました。
 (今後に向けて)義務教育9年間の中で計画的、継続的に学力の充実が図れるよう、小中連携の取組を一層進める必要があります。 (今後に向けて)義務教育9年間の中で計画的、継続的に学力の充実が図れるよう、小中連携の取組を一層進める必要があります。 |
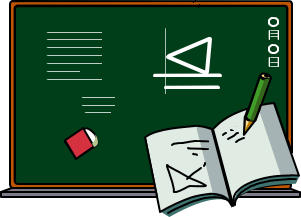
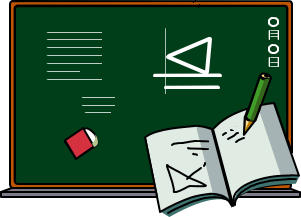
![]()
![]() 基礎学力充実実践研究事業とは?
基礎学力充実実践研究事業とは?![]() 平成14年度の取組
平成14年度の取組![]() 平成15年度の取組
平成15年度の取組![]() 平成16年度の取組
平成16年度の取組